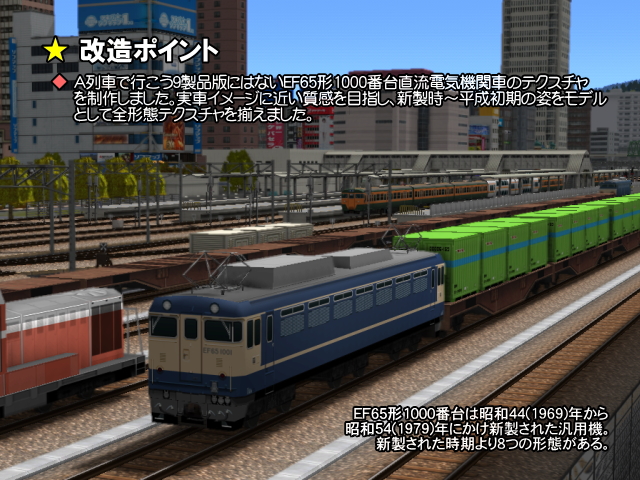|
model [1] EF65形1000番台 一次形(1001~1017号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1001 |
一次形は1969(昭和44)年、寒冷地対策が不十分なまま運用され、故障が多発していた東北本線貨物列車牽引のEF65形500番台(F形)置換えのため新製されました。(名目上は東海道・山陽本線の貨物増発)
EF65形500番台運用で問題になった重連総括制御用の引通線を両渡り構造として貫通路を設置、ヒーターなど凍結対策を強化していました。新製当時はツララ切りはありませんでしたが後に追加設置されています。(前照灯には廃車まで設置されなかった)
EF65形1001号機は新製投入された宇都宮運転所に永く在籍し、国鉄末期に一時関西での運用が行われた以外一貫して東日本で運用されました。この間、寝台特急「あけぼの」牽引運用にも当たったこともあります。国鉄分割民営化時にJR貨物へ継承、2008(平成20)年まで運用されました。
最後まで原形を保っていた1両であり、Hゴム黒色化などの形態変化はありませんでした。
現在はJR貨物中央研修センターに保存(車籍はあり、廃車扱いとなっていない)されています。
EF65 1001
1969.10新製(東海道・山陽本線増発) 配置:宇都宮-新鶴見-宮原-吹田-新鶴見-JR貨物継承 |
|
 |
model [2] EF65形1000番台 一次形(1001~1017号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1011 |
EF65形1000番台車は装備が示すように寒冷地を走行する運用に適した仕様であったことから東北本線に集中投入されます。(1979年には51両が宇都宮運転所に配置)主目的ある貨物運用はもちろん、
12系や24系と言った牽引機を選ばない旅客運用にも充てられるようになります。こうした背景の中でEF15形、EF58形と言った旧式機が引退する中でEF65形1000番台は運用範囲を拡大しました。
1011号機は宇都宮運転所生え抜きの1両で、国鉄分割民営化時JR東日本に継承されました。当時全盛だったジョイフルトレインや定期運用の旅各列車の先頭に立ちましたが、旅客会社のEF65形は客車列車の減少により1990年代急速に余剰となります。こうした中で
1011号機は1995(平成7)年廃車となりました。これは貨物会社継承機を含むEF65形1000番台で最も早いものとなりました。
EF65 1011
1969.10新製(東海道・山陽本線増発) 配置:宇都宮-田端-稲沢-田端-JR東日本継承、1995.4.5廃車 |
|
 |
model [3] EF65形1000番台 二次形(1018~1022号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1018 |
二次形以降、EF65形1000番台車は一次形で装備しなかったツララ切りを最初から装備していました。また、外観上は変化ないもののカニ22形のパンタグラフスイッチが撤去され、
一人乗務に備えてEB装置・TE装置の設置、記録式速度計の搭載など、運転室関係の改良が行われています。平坦線区の万能機と言われたEF65形1000番台車は本来の運用地以外で一時的に運用されています。この一時的な運用先で改修によって外観の変化した車がいます。
1018号機はそんな1両で、新鶴見機関区へ配置後、1973(昭和48)年から2年あまり下関運転所で運用されたのですが、この下関在籍中、ナンバープレートをブロック式に改造されています。
1018号機は下関から関東に戻ったあとそのまま東日本で運用、国鉄分割民営化時JR東日本に継承、1996(平成8)年余剰により廃車となりました。
EF65 1018
1970.1新製(新空港建設資材輸送) 配置:新鶴見-宇都宮-下関-宇都宮-田端-JR東日本継承、1996.11.7廃車 |
|
 |
model [4] EF65形1000番台 二次形(1018~1022号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1021 |
二次形は5両のみの小区分でした。続く三次形で車体に変化があったためですが、この二次形は1970年以降山陽本線波動輸送強化と関西-九州間寝台列車増発などにより逼迫した機関車需給の
都合上、全機下関運転所に配置となっていました。その際機番プレート式に取り替えられています。該当機は後にレインボー塗装となる1019号機を除く4両全てでした。(三次形の1023~1025号機、五次形の1054号機も改造されている)後に六次形以降でプレート式機番表示を
新製時から採用していますが、こちらはステンレスエッチング標記で、従来の切り文字のままプレート化された改修機とは違う点です。何故手間のかかったであろうこのような改造が行われたのかはっきり記述した資料が見つかりませんでした。
1021号機は下関から関東に戻ったあとそのまま東日本で運用、国鉄分割民営化時JR東日本に継承されましたが、従来研き出しだった機番は白塗装となっています。1997(平成9)年余剰により廃車となりました。
EF65 1021
1970.4新製(万博輸送、呉線電化) 配置:広島-下関-宇都宮-田端-JR東日本継承、1997.9.2廃車 |
|
 |
model [5] EF65形1000番台 三次形(1023~1039号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1033 |
三次形は車体形状に変更が加えられた区分で、貫通扉下側のステップの長さが手すりの内側まで短縮されています。呉線電化・高島線電化・特急客車列車増発・東北本線・高崎線貨物列車増発・
身延線機関車形式改善を目的に増備され、予算区分上三次形までが初期の増備となりました。引き続き宇都宮・新鶴見・広島・下関の各所に配置され、増発あるいは従来機の転出の原資とされています。
前述の通り三次形でも1023~1025号機がプレート式に改修されていますが、本テクスチャではオリジナルの車をテクスチャ化しています。EF65形1000番台初期車はその後一旦宇都宮運転所への集中配置を後に、各地へ転出(一時期は51両が配置、1984年)しています。1033号機は
国鉄分割民営化によりJR貨物へ継承、更新改造によりJR貨物色へ変更されています。
EF65 1033
1970.9新製(呉線・高島線電化、増発、身延線形式改善) 配置:宇都宮-田端-新鶴見-JR貨物継承-岡山-JR貨物色化(1997.3)2010.3.31廃車 |
|
 |
model [6] EF65形1000番台 四次形(1040~1049号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1041 |
四次形では設計変更があり、扇風機設置による運転台下の通風口廃止・尾灯の新形化(外はめ式)・メンテナンスフリー化を図ったバーニア制御器,界磁制御器の変更・メートルねじの採用が行われています。
また、使われなくなっていたKE59形ジャンパ連結器(20系客車兼引用)が省略されたもののスカートの形状は従来のままで、省略されたジャンパ連結器の場所は穴が開いたままとなっていました。
1041号機は国鉄分割民営化時JR貨物へ継承されていますが、更新工事や改修はおろかHゴムの仕様変更もなかったため、廃車となる2012(平成24)年まで国鉄時代そのままの姿を保ちました。
EF65 1041
1972.7新製(東北本線の増発、飯田線線形式改善) 配置:宇都宮-田端-新鶴見-JR貨物継承-高崎2012.9廃車 |
|
 |
model [7] EF65形1000番台 五次形(1050~1055号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1053 |
五次形は四次形の様な大幅な設計変更はなく、四次形で間に合わなかったスカートの形状が変更となり穴がなくなったことと、継電器の変更に伴う抵抗バーニア制御器の形式変更があっただけでした。
全機が山陽本線の波動輸送強化のため下関運転所に配置となっています。
1053号機は国鉄分割民営化時JR東日本に継承されたうちの1両で(JR東日本継承のEF65形1000番台車は1011,1013~1030,1052,1053,1098~1116,1118の41両)同社に継承された電気機関車の大半がそうであった様に、客車列車の減少やJR貨物の輸送業務委託解消により余剰廃車の道を辿りました。
1053号機も廃車まで原形を留めています。
EF65 1053
1972.9新製(山陽本線の波動輸送) 配置:下関-広島-新鶴見-田端-JR東日本継承2001.8.1廃車 |
|
 |
model [8] EF65形1000番台 五次形(1050~1055号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1054 |
前述の様に五次形は全機山陽本線の波動輸送強化のため下関運転所に新製配置されました。この時期下関運転所配置となったEF65形1000番台は従来の切り文字式機番表示からブロック式ナンバープレートに
変更された車があり、1054号機もこの対象となりました。ところがこの1054号機のみ、プレートの大きさが他車とは異なり大きなものを装備していた点が特異な点です。(1054号機以外は六次形で採用されるブロック式と同じ大きさ)
国鉄分割民営化でJR貨物に継承された1054号機ですが、EF65形1000番台車の多くが延命・更新工事を受ける中、1054号機はこの改修から漏れ、わずかにHゴムの黒色化(窓ガラスの交換)が行われたに留まり、廃車まで特徴あるナンバープレートを装備していました。
EF65 1054
1972.9新製(山陽本線の波動輸送) 配置:下関-広島-新鶴見-高崎-JR貨物継承-新鶴見2010廃車 |
|
 |
model [9] EF65形1000番台 六次形(1056~1091号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1062 |
EF65形1000番台の増備は昭和46年度債務の五次形までで一旦終了していましたが、1976(昭和51)年から増備が再開されました。六次形はそれでの運用拡大・列車増発目的ではなく、
首都圏の旧式機の置換え(対象はEF10・12・13・15形)が目的で、一気に36両が増備されました。五次形との相違点は難燃化の推進・パンタグラフの変更・ブロック式ナンバープレート(ステンレスエッチング仕様)の採用・避雷器の変更・電気火災事故防止のための対策
などの安全性・メンテナンス性向上を図るための施策が挙げられます。
1062号機は国鉄分割民営化でJR貨物に継承されましたが、EF65形1000番台六次形以降の車が軒並み更新・延命工事を受けたのに対し、廃車まで未施工だった車だった1両にあたり、廃車時期も早いものでした。(JE貨物で更新・延命工事が行われなかったEF65形1000番台
六次形は1056,1059,1062,1064,1071~1073,1078,1079,1082のみ)
EF65 1062
1972.9新製(首都圏の旧機置き換え) 配置:新鶴見-高崎-JR貨物継承2009.3.31廃車 |
|
 |
model [10] EF65形1000番台 七次形(1092~1118号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1100 |
七次形は長距離高速運転による酷使で故障が多発していた東京口寝台特急牽引のEF65形500番台を置き換える目的に1978(昭和53)年に東京機関区へ集中増備された1097~1116号機を含む区分です。
東京区のEF65運用はハードで、月に2回も交番検査が必要となるほどの運用距離に達していました。このため、保守の合理化を目的に重連・寒冷地装備の使用停止(ホース類・スノープロウの取り外し、砂撒き管ヒーターの配線カット)が行われました。EF65形1000番台は六次形
でほぼ完成形となり七次形では前述の運用上の行われた処置以外外観上の変更点はありませんでした。(窓ガラスの5mm強化ガラス化が行われているが外観上差異はない)
1100号機は東京口の寝台特急運用に充てられましたが、1985(昭和60)年のロビーカー増結による牽引定数オーバーのためEF66形に運用を譲り(一部はEF65形運用で残されている)一般運用に振り向けられています。国鉄分割民営化でJR東日本に継承、2008(平成20)年3月の寝台急行
「銀河」の廃止に関連してか同年6月に廃車となっています。
EF65 1100
1978.6新製(紀勢本線電化、旧型電機置換え) 配置:東京新-新鶴見-田端-JR東日本継承2008.6.16廃車 |
|
 |
model [10] EF65形1000番台 八次形(1119~1139号機) 国鉄特急色 仕様
EF65 1134 |
EF65形1000番台最後の増備である八次形は一次形の増備開始から実に10年を経て増備されたグループでした。この間様々な改良が行われ、六次形でほぼ完成形となっています。八次形では主電動機・
避雷器の変更、台車枠の溶接強化や台車の部品取付方向変更など外観上にほとんど差異に影響しない改良が行われたのみでした。(八次形は関西-九州間の寝台列車牽引を目的としていたため、西日本に集中投入された結果、耐寒耐雪設備のうちスノープロウ・汽笛カバー・砂撒き
管ヒーター・主電動機用歯車箱の防雪カバーを省略している)
1134号機は宮原機関区配置、関西-九州間の寝台特急運用にあたり、そのままJR西日本に継承されましたが減便と連結両数減少に伴い行われた牽引機交代により2000(平成12)年以降定期運用はなくなり、以降は臨時列車牽引や事業用に使用されています。
EF65 1134
1979.7新製(関西圏旧式車置き換え) 配置:宮原-吹田-下関-JR西日本継承-JR貨物譲渡-新鶴見-高崎2009.3廃車 |
|